2009/4/9 New!
皆様の熱い要望にお応えして、「勇者死す。」にディレクターズカット版が登場!
2009年5月、NTTドコモ公式サイト『R.P.G-mode』にて配信予定です。お楽しみに!!
http://www.g-mode.jp/title/hero/index.html
バランスをいじって、エンディングの数を増やしてみた。
ということで、この機会にまだの方はぜひどーぞ。
2009/4/9 New!
皆様の熱い要望にお応えして、「勇者死す。」にディレクターズカット版が登場!
2009年5月、NTTドコモ公式サイト『R.P.G-mode』にて配信予定です。お楽しみに!!
http://www.g-mode.jp/title/hero/index.html
バランスをいじって、エンディングの数を増やしてみた。
ということで、この機会にまだの方はぜひどーぞ。

去年から某氏とチョコチョコと話をしていたゲームの企画がお流れになったという知らせが昨夜あった。
楽しみにしていたので非常に残念だ。
大きめの企画なので、当分実現しそうもないから、企画内容を忘れないようにメモがわりにここに記しておく。
大枠は、多人数参加型のアクションRPGだ。
見た目は今どきのMMOを適当に想定してほしい。
本企画のシステムが既存のRPGと大きく異なる点は以下の3つ。
●金は相場で稼ぐ:
本企画でも通常のRPG同様、モンスターを倒したりダンジョンで得たアイテムを換金したり、あるいは依頼を受けて報奨金を得るなどの手段で金を得ることはできる。
ただし、これらの方法で作った金は、本企画では相場を張るためのタネ銭程度の位置づけだ。
つまり、通常のRPGの感覚ではいつまでたっても金持ちになれない。
では何で儲けるかといえば、「相場」だ。
本企画の世界には、大ざっぱに言うと三すくみの関係にある属性が三種類存在する。
この属性は、モンスターの種類、魔法の体系、装備や消費型の魔法アイテムの材料になる「元素」の属性など、この世界のあらゆる要素に共通して存在する。
このアイテムの材料になる元素が、街で取り引きされ、相場が形成されている。
この相場を、全プレイヤーが共有する。
で、簡単に言えば、プレイヤーは、今後値が上がりしそうなアイテムを予想し、相場の安いときにそれを買い、値段が上がったところで売ることにより利益を得る。
さて、相場の上がり下がりはなぜ起きるか? 何を根拠に予想するか?
●生態系への干渉:
先に述べたとおり、この世界では三すくみの関係にあるモンスターが、大別して三群存在する。
(話をわかりやすくするために、三すくみのそれぞれを「グー」「チョキ」「パー」と仮称する)
三つの属性のいずれかをもったモンスターが、各フィールドごとに固有の割合で分布している。
たとえば、湿地帯のフィールドでは、グー6:チョキ3:パー1の比率とか、草原のフィールドならグー2:チョキ3:パー5とか、そんな感じだ。
この比率がプレイヤーが特定の属性のモンスターを集中して狩ることで一時的に変化する。
たとえば、先の湿地帯を例にとると、グーのモンスターを大勢のプレイヤーが集中して倒しまくれば、「グー6:チョキ3:パー1」が「グー2:チョキ6:パー2」の比率に変わる。
上記「金は相場で稼ぐ」の項で書いた「アイテムの材料になる元素」は、原則的にモンスターが落とす。
ということは、どうなるか?
「グー6:チョキ3:パー1」の状況では、パー元素の相場はグーの6倍、チョキ元素の相場はグーの2倍であったものが、「グー2:チョキ6:パー2」になるとグーとパー元素の相場がチョキの3倍に“近いうち”になると予想できる。
(ちなみに元素の相場が変動すれば、それを使って作る武器や魔法アイテムの値段も変わる)
ところが、この“近いうち”が実は曲者だ。グーのモンスターが減ったということは、グー元素の在庫を山ほど抱えているプレイヤーが大勢いるということだ。
誰がいつそれを市場に出すか? 腹の探り合いになる。
また、そうこうしている間に草原フィールドで他のプレイヤー群が、チョキのモンスター狩りを大規模に仕掛けた、あるいは仕掛け「そうだ」という噂を聞いたら、どうなるか?
さっ、想像してみてくれ。
●噂とニュース:
ひとりのプレイヤーがいくらがんばったところで、生態系に与える影響は微々たるものだ。
ということは、他のプレイヤーを自分の思惑に巻き込むか、他のプレイヤーの思惑に乗っかるかだ。
その手段として、チャットで噂を流し、掲示板で同士を募集。
たとえば、有力なプレイヤーが「パーを狩りに行こうぜ」と呼びかけ、数人が賛同しただけで相場が動く。
その連中がダンジョンに行くのを見るだけでまた動く。
相場や生態系に大きな動きがあった場合は、ニュースとして全プレイヤーに公開される。
有力なグループがある属性の元素にどんどん買い注文を出していたら? なにかあると読んで同じものを買う?
また生態系の変化は、気象にも影響を受ける。そのためこの世界内の天気予報は重要な情報だ。
以上
●どこまでが夢だ? 2009年02月27日
僕は中学生で、修学旅行中の写真が中学校の掲示板にいっぱい貼りだされていた。
見れば、一枚百円もした。
帰宅後
「スナップ一枚百円だってさ。あこぎだよね」と母親に話したつもりが、なぜか話した相手は妻で、
「なに寝ぼけてるの? あなたは49歳で中学生じゃないよ」と言われた。
――というところで、目が覚めて、そういえば
「次男の修学旅行費の振込みが確か今日までだったよなあと、気にしながら寝たから妙な夢を見たのだろう」と気づいた。
――というところで、もう一度目が覚めて
「どこまでが夢だ?、というタイトルで日記を書こう」と思った。
――というところで、さらにもう一度目が覚めた。
↑今、ここ。
これは、どうやら夢じゃないらしいが、確たる自信はない。
で、時計を見たら13時半。
あ、次男の修学旅行費、振込みに行かなきゃ!
うわっ、雪が降ってるよ。
●10年間隔で進化する夢 2009年03月17日
繰りかえし見る夢がある。
空中を遊泳する夢だ。
この内容が緩慢だが、少しずつ不思議なことに進化している。
10代の僕は、夢の中で車や建物を信じがたいジャンプ力で飛び越すことができた。
20代に、大きくジャンプして落下する際、手を広げることで滑空する術を徐々に覚えた。
30代では、滑空時間が長くなり、路面をスレスレに滑空したり、その状態で方向転換することができるようになった。
だが、まだ「飛ぶ」ことはできなかった。
飛べるようになったのは、40代になってからだ。
路面を滑空している状態で、道を押すように手を動かすと、少しだが浮上することを発見した。
これを繰りかえすことで飛び続けることができた。
が、滑空の途中で再浮上するのは、力の加減が難しい。
弱いと失速して着地してしまうし、強すぎると空中で身体が反転してしまい、やっぱり失速して落ちるのだ。
だから、力の加減に神経を使って、飛ぶことが楽しくなくなった。
今朝の夢で、ついにバランスの悪さを克服した。49歳の春だ。
なんと空中遊泳の師匠が夢の中に現れたのだ(笑)。
「両手に水の入ったやかんをぶら下げているイメージを持て」と僕に助言してくれた。
最初は上手くいかなかったが、徐々にコツをつかみ、空の高いところまで気分よく昇れた。
この調子なら、僕が死の床で見る夢は文字通り「昇天する」夢だろうと目が覚めたときには直感したが、それじゃああまりに捻りがなくてつまらないかと今は思う。
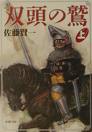


●双頭の鷲 佐藤賢一著
「傭兵ピエール」が面白かったので、続けて同じ作者の代表作を読んでみた。
こっちのほうが面白いな。
というか「えへ、えへ、えへ」とか品のない笑い方で、馬糞を鷲づかみにするメチャクチャなキャラを“英雄”にしようと思いつき、実行した時点で、エンターテイメントとしてはもう勝ちだろう。
ちょっと反則くさいが、面白ければなんでもアリだ。
しかし、これ、フランス人が読んだら、どう思うんだろうね。
たとえば、源義経や坂本竜馬が、実は、「えへ、えへ、えへ」とか品のない笑い方で、馬糞を鷲づかみにする人物だった……とフランス人が書いたら……。
あ、面白いね、ぜんぜん問題ないや。
●狐笛のかなた 上橋菜穂子著
人外や超能力者が多数登場するわりには、驚くような仕掛けもない収まりのいい話だ。
ポイントは、ストーリーよりも郷愁を感じる世界観だろうか。
空気がとても心地いい。
こんな和の世界観の中で暮らせるゲームならプレイしてみたい。
昨今のゲームは、海外市場を念頭に置いた企画しか通りにくい傾向にある。
が、こういうしっかりした背骨がある和の世界感のほうが、むしろ世界に通用する気がする。
それと、献身的に働く健気な狐の使い魔。
僕も、夜鳥子2巻から準レギュラーで出したけど……やっぱカワイイよ。
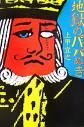

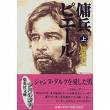
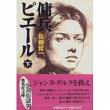
●地獄のババぬき 上甲宣之著
2009年01月01日
昨夜、ちょっとだけ読もうと思って開いた500ページ近い小説、一気に読んでしまいました。
寝るのを忘れて夢中で本を読むなんて久しぶりだったので、妙に清々しい新年のスタートとなりました。
その本のタイトルは「地獄のババぬき」
作者は上甲宣之さん。
中身を一言で表せば「全力であほらしい」です。
天才マジシャン、稀代のギャンブラー、深層心理学専攻の女子大生、超能力少女、殺人鬼……、このあたりの濃いメンツが命がけで「ババぬき」をする。
それだけで500ページ。
読み終えても、感動はもちろん何にも残りません。
いやあ、あきれたね(笑)
素晴らしいよ、この潔さ。
何年か前に話題になった少年少女が最後のひとりになるまで島で殺し合いをやる「バトルロワイヤル」、あれに近いあほらしさです。
間違っても、社会に対する風刺とか問題提起だとか、そんなもんを読み取ってはいけません。
断言するけど、作者はそんな面倒なこと毛の先も考えてませんから。
意識して、ちょっと影響されてみようかと思います。
●とある飛空士への追憶 犬村小六著
2009年02月08日
中学受験のシーズンが終わり、娘が通う神保町の塾の時間割が変わった。
それはともかく、行きの電車の中でフロスト警部の新刊(?)を読んでいる人を発見。
ちょうど読む本がなかったので、買おうと思って入った本屋で、なぜか買ってしまったのがタイトルの本。
表紙の女性が凛々しくてつい手にとってしまいました。
最近、夜鳥子の完結編の評判を読みに、あちこちのブログを徘徊していて、よく話題になっていたので、なんとなく表紙の絵を覚えていました。
中身は、次期皇女の姫君を敵地の真ん中を単機で突っ切って、味方のところまで無事送り届けよと命を受けた、最下層民の飛行士の苦労と切ない恋の話。
好きだねえ、こういう3行くらいで粗筋が書けちゃうようなシンプルで真っすぐな話。
雑念だらけの僕には、逆立ちしても書けないけど、一読者として好きだなあ。
人気がある理由もよくわかる。
そういえば、ほめるときを除けば、一読者とか一プレイヤーとして、口を開くことがいつの頃からか少なくなった。
だって、「***のここは酷えと思う」と僕が書いた瞬間、前後の文脈をすっ飛ばしてネット上のあちこちにずっと残るものねえ。
いわく、「自分の駄作を棚に上げて、偉そうなことを。マスダ、氏ね」とか(笑)。
いやまあ、それなりのお金を払って、自分が期待してたモノが手に入らなかった人たちにとっては、そのとおりなのかもしれないけど。
僕だって、一読者や一プレイヤーで、お金を払って期待を裏切られることは多々あるよ。
で、面倒くさいから、「僕はゲームをしません」と言ったら今度は「ゲームもしないのに、わかった風なこと言いやがって、氏ね」と(笑)。
でも、しょうがないんだろうね、プロだし。
ついでに、先日「バカだバカだ」と絶賛した「地獄のババ抜き 上甲宣之著」の前の話に当たる「そのケータイはXX(エクスクロス)で」も読みました。
面白かったけど、このレベルのバカさ加減なら、構造を解析すれば僕にも書けそうだという意味で「バカだバカだ」と絶賛するほどじゃなかった。
あ、ということはこの作者は書くたびにバカ度がアップしてるということかな。
だとしたら素晴らしい。うらやましい限りだ。
●傭兵ピエール 佐藤賢一著
2009年02月24日
島田洋七の話に似てる。
最初はホント(史実)とウソ(創作)の区別がつかない。
ウソだと気づいた頃には、本当かウソかなんてどうでもよくなり、ウソを楽しんでる。
中盤あたりで話がしばらくグダグダするが、最後までこの壮大なホラ話に付き合ってやろうと思えるくらい勢いがあった。
エンターテイメントは、こうじゃなきゃね。