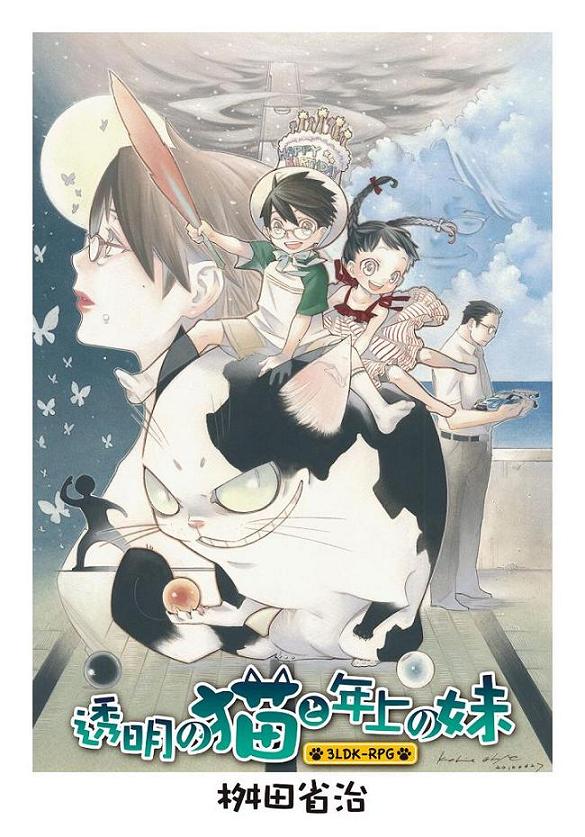2月19日(金)、ハヤカワ文庫JAより発売。
というわけで恒例のたっぷり試し読みです。どーぞ。
序章 禁断の媚薬
山羊の初乳を二カップ……、イモリの尻尾を根元から二ミリ……、
金ザクロを二粒……、満月の夜に掘りだしたニンニクとショウガを各二かけずつ……、
コーヒー豆の粉を二グラム……、イボガエルの脂汗を二匙……。
最後に、いくら魔道を志す者とはいえ、うら若き乙女が中身の正体を口にすべきではない赤黒い液体を二滴たらす。あとは焦げないように辛抱づよくトロトロと煮つめるだけ。
マリーベルは暗闇の中、小さなロウソクの明かりだけを頼りに一心に作業を続けていた。
彼女は、この種の作業に明らかに慣れているらしい。材料を量るときは実に用心深いが、計量後の材料を小さな鍋に次々に放りこんでいく手際は驚くほど大胆だ。
にしても……、秋の夜とはいえ閉めきった部屋で長時間火を使うとさすがに暑い。加えて、ひどくにおう。おかげで服は汗でぐっしょり。赤い髪と服に染みついたニオイは、一度や二度洗ったくらいでは到底とれそうもない。だが、窓もカーテンも開けるわけにはいかなかった。この薬は、誰にも知られずに完成させねばならないのだ。
ここは、王都ヤルタバードにある魔道士養成学校の薬品管理庫。闇の中に巨大な棚が何本もぼんやりと浮かんで見える。棚の中には世界中から集められた薬の材料が所狭しと並んでいる。圧巻は、今しがた切り取ったばかりのような大猿【ルビ:マンドリル】と虎の生首の瓶詰め。他には、何のものかはわからないが目玉や舌が詰まった瓶もある。それにオットセイのアレ、黒サイのアレ、ユニコーンのアレ、パンダのアレ、以上は干物……いやはや。
今は月曜日の深夜、午前一時を少々回っている。あと十二時間ほどで騎士養成学校との合同卒業式が始まり、そのあと場所を王宮の大広間に移して盛大な謝恩会。
そのパーティ会場で、マリーベルはある計画を秘密裏に実行するつもりだ。その準備に一年を費やした。薬学の先生の信頼を勝ちとり、薬品管理庫の鍵をこっそりと盗みだし、きのうの午後からずっと便所に隠れ、校内から誰もいなくなるのをひたすら待った。
しくじるわけにはいかなかった。マリーベルは、この企てに全身全霊を賭けていた。なぜなら、その成否が自分の一生を左右するだろうし、おそらくはこれが最初で最後のチャンスだと思えたからだ。手段を選んでいる余裕はない。必死だった。
ところで、だ……、
魔法の秘薬を一度でも作ったことがある読者なら冒頭に挙げた材料を見て、すでに「ああ、アレね」とお気づきのことだろう。マリーベルが作っているのは、ちょっとアブナイ薬。いわゆる“禁断の媚薬”であることは説明するまでもない。
この時代、ことにこのウルカン王国においては、本物の魔法はともかく魔道士が作る秘薬くらいはさほど珍しくない。手頃な価格とは言いがたいものの広く流通している。だがそれでも、今マリーベルが作ろうとしている薬は、もしも発覚すれば両手が後ろに回るくらいには、やっぱりちょっとアブナイ。そういう類のものだ。
――そんな物騒な代物を危険を冒してまで作り、彼女は誰に使おうとしているのか?
その答は少し後回しにして、先にマリーベルの「聞くも涙、語るも涙(本人談)」の生い立ちを簡単に紹介しておこう。
マリーベルの父は、秘薬の製法に長じた魔道士。その筋では百年にひとりの天才とうたわれていた。ここ四半世紀の間に画期的な薬が五つ開発され、そのうちの四つはマリーベルの父が手がけたもの、残りのひとつもそのアイデアがその死後に弟子のひとりによってカタチになったものだ。
マリーベルの父は偉大だった。だが、天才とナントカは紙一重という言葉どおり、大事な何かが欠けていたにちがいない。新薬を自信満々で弟子と使用人と家族と父本人の身体を使って実験し、その全員の命をあっさりと奪いさったのだ。当時七歳だったマリーベルと弟子のひとりだけが助かったのは、たまたまその日風邪をひいていて別の薬を飲んでいたため、実験から外されたからにすぎない。
社会に与える影響が大きすぎるとの政治的判断をどこかの誰かが勝手にくだしたのだろう、この忌まわしい事件は闇に葬られた。それと同時に数百年続いた一族の姓“ベルリア”も貴族と魔道士の名簿の両方から完全に抹消された。
マリーベルもまた社会の片隅で生きていくために、姓も名も変えざるをえなかった。今は、元の名前マリーにベルリア家のベルをつけて、マリーベルと名乗っている。現在の姓“ビパイア”は、彼女を引きとった貧民街で暮らす母方の遠戚のものだ。
この遠戚は、表では無資格の医療行為を行い、裏では非合法かつ粗悪な薬品を製造して生計を立てていた。マリーベルが秘薬の調合に秀でているのは、その裏稼業を物心ついたときから手伝わされていたため、それに父譲りの天賦の才が小匙一杯半ほど……。
魔道士養成学校は、上級魔道士の子女のために作られた学校だった。貧民街で暮らすマリーベルなど逆立ちしても入れるようなところではない。だが、入学した。それも特待生。ただし、成績が飛びぬけて優秀だったわけではない。
これには大人の事情がある。この学校の校長の名は、ケルビン・メリクリス。この男こそ、マリーベルとふたりだけ生き残った父の弟子であり、父のアイデアを盗んで新薬を作り、その功績により現在の地位を得た人物だった。
マリーベルは校長と取り引きした。入学金、授業料、寮費など一切合財の諸費用の免除と交換に卒業時に父の形見である日記を引き渡すという条件だ。日記には校長が発明したはずの新薬の製法が記されていた。
有体【ルビ:ありてい】にいえば、五年前、トリガラのように痩せた十三歳の少女は、王立高等学校の校長を“立派に”恐喝したわけだ。これは、秘薬の調合とともに貧民街で会得した、生きていくために必要な基本技術のひとつ。ようするに彼女は、名前を変えたのち、そういう種類の人間になっていた。
そんなマリーベルにも少女らしい純情さが小匙一杯半ほど残っていた。それは、魔道士養成学校を志望した理由だ。資格を得て手に職をつけ、社会の底辺から這いあがりたい。お金を稼いで美味しいものを食べたいし、たまにはきれいなドレスも着てみたい。そういうありふれた願望ももちろんあった。だが、それだけなら、父の日記をネタに校長をゆするほうが手っとり早くはるかに簡単だ。
▽▽▽ ジョン・アスタロット ▽▽▽【▽は、白抜きのハートマーク。以降同じ】
貧民街で暮らしはじめたマリーベルに初めて普通に声をかけてくれた同い年の男の子。ジョンは、川向こうにある地方貴族の子弟が通う小学舎の生徒だった。
他の者はマリーベルを「ベル」と呼んだが、なぜかその男の子だけが「マリー」と呼んでくれた。それが泣きたいくらい嬉しかったことを覚えている。
ジョンは、マリーベルの初恋の相手だ。その想いは十年がすぎた今も変わっていない。
その愛しいジョンが騎士養成学校に進学すると風の噂に聞いた。マリーベルは少しでも恋人の近くにいたかった。だが、騎士養成学校は男子校。そこで、隣接する魔道士養成学校に潜りこむことにしたのだ。
五年間でしゃべったのは三回だけ、それも軽い挨拶。でも、時おり生垣の向こうに愛しい彼の姿を見つけるだけで幸せだった。だが、そんな至福の時も今日の卒業式で終わる。
だから、そして、もちろん――
マリーベルがちょっとアブナイ薬を盛ろうとしている相手は、他でもないジョンだ。
媚薬の力を借り、気分が高揚したジョンに謝恩会の会場でプロポーズさせる。それがマリーベルの計画、一世一代の大勝負だ。
「マリー、ずっと君が好きだったんだ!! 俺と結婚してくれ!!」
「あたしはその言葉を待っていたのよ▽ 愛してるわ▽ ジョン▽」
ふたり分の会話をひとりで演じながら、妄想はさらに進む。
――そうだ!! ジョンとふたりで薬を行商して国中を旅するのも楽しいかもしんない。で、お金を貯めて小さな家を買って、子供を作るのはそれからでもいいかな? 最低でも男の子と女の子ふたりずつは欲しいわね。名前も考えなきゃ。
そんな遠い未来のことまで夢見ながら、マリーベルは目の前の鍋をゆっくりとかき回した。そして、鍋底でフツフツと沸き立つ虫の卵のような白い小さな泡に誓う。
「やってやるよ!! 絶対にジョンをあたしのものにしてみせるんだ」
闇の中でもわかるほど赤いマリーベルの唇がニンマリと歪んだ。
さて、彼女がこれほどまでに想いを寄せるジョンという男、どんな若者なのだろう?
次章冒頭から噂のジョンが登場!! はたしてマリーベルのアブナイ恋は実るのか?
一章 プロポーズは突然に
―1―
どう考えてもこのままじゃヤバイ……。卒業までになんとかしなきゃいけない。
それは何年も前からわかっていたが、結局なんともならないどころか、解決の糸口すら見出せないまま、就職の当てもなく卒業式を迎える羽目になってしまった……。
同級生よりほんの少し運が悪く、夢とプライドが空回りしている分、無駄に熱量だけが高い。理想と現実のギャップにしばしば悩み、世間の理不尽さに腹を立てるのにも疲れ果て、「どうせ……」がそろそろ口癖になりかけている。ジョンは、いつの時代どの国にも掃いて捨てるほどいる青くさい若者だった。
ジョン・アスタロットは、没落しかけの貧乏貴族の子弟として生まれた。親の財産は、北の果てにある石ころだらけの狭く痩せた領地。それを長男が継承するのが決まりだ。次男は長男に不慮の事故があったときの予備として、自動的に実家で居候の身分となる。そして、三男以降はただの厄介者。なんの期待もされていない。極端な話、死亡通知を受け取るまではどこで何をしていたのか、実家は関知しない。ジョンは三男だった。
それでも親兄弟に財産か地位か名声か、そのひとつでもあれば、あるいは本人に何か秀でた才能がひとつでもあれば、娘しかいない貴族の家に婿養子として迎えられる場合も珍しくはない。だが、ジョンにはどれひとつなかった。
ジョンが在籍している学校は、騎士養成学校というくらいだから、騎士を養成する学校にはちがいない。ジョンはその名称を素直に信じて、卒業すれば王宮詰めの騎士になれるものと思いこんでいた。そのための努力も人一倍したつもりだ。
だが、現実はそんなに甘くなかった。
入学してみてわかったことだが、同級生はジョンと同じ、貴族の次男三男四男五男が大半だった。違っていたのはジョンの境遇よりは、ずいぶんマシだったこと。つまり親兄弟に財産か地位か名声のどれかがあり、それを皆が切り札として隠し持っていた。
そして、卒業を控えた年になってやっとわかったのは、切り札をよりたくさん持っている者から順に、王宮詰めの騎士の採用枠を埋めていくということだ。それじゃなくても不景気続きで今年から募集人員が減ったというのに、だ。
もちろん、学業の成績が優秀であるほうが有利なのは確かだし、努力が実らないわけでもない。そこは公平だ。ただし、成績や努力が考慮されるのは、手の中にある切り札の数が同じ場合のみ。元もと切り札が一枚もないジョンには、まったく関係がなかった。
マリーベルが、ちょっとアブナイ薬を朝方までかかってやっと完成させた同じ月曜日の午後、王都ヤルタバードの空はどんよりと垂れこめた雲におおわれていた。
その曇り空そっくりな気分のジョンは、晴れやかな式服に身を包み、同級生たちとともに騎士養成学校と魔道士養成学校の合同卒業式に参列していた。
式典用の制服は、金色の肩章がついた鮮やかな青いジャケット、襟には白いマフラー。下は、七分丈の真っ赤なズボンに白いストッキングをはいている。幅が狭いつばがついた青いフェルト帽子の正面には、火喰い鳥の巨大な赤い羽飾りが唐突に立っている。
こういう特別な場以外ではマヌケに見える、時代錯誤も甚だしい大仰なデザイン。おまけに着るのは年に二、三回。なのに、決して安物ではない。それでも同級生の大半は卒業式のためにわざわざ新調していた。だが、ジョンは長男次男のお下がりだ。誰が見てもジャケットもズボンもヨレヨレで袖も裾も短いのがわかる。それに帽子の羽飾りも今の心境そのままに下を向いてしおれていた。
礼拝堂を兼ねた講堂には、同校の最高学年である五年生と、隣接する魔道士養成学校の五年生、合わせて二百人ほどが左右二つに分かれて整列していた。その周りを生徒の倍ほどの父兄が囲んでいる。皆、立ったままではさすがに居眠りできないらしく厳粛な面持ちで壇上を見つめている。当然ながらその中にジョンの家族はいない。
市長だの騎士団長だの将軍だの大臣だの今日初めて見るお偉方が次々に壇上に現れては、希望だの未来だの仕事だの誇りだの、ジョンにはおよそ縁がない言葉を延々滔々【ルビ:えんえんとうとう】と並べている。
演壇の背後には、真っ白な獅子トカゲにまたがった初代国王“聖ウルカ”の姿を写した青地の国旗が天井から垂らされていた。その左右には親に手を引かれた子供のような配置で、王家の旗よりひとまわり小さい両校の旗が小じんまりと飾られている。
お歴々のご祝辞が盛大な拍手をもって終わると、残る式次第は卒業証書の授与のみだ。名前を呼ばれた生徒が次々に壇上にあがり、紙切れをありがたそうに受け取っていく。
ジョンは、自分の名前が呼ばれない奇跡を神に祈っていた。名前を呼ばれて証書を受けとれば卒業だ。その瞬間から気軽な学生の身分は剥奪され、明日からは無職。新入生が来れば朝夕の食事が保証された寮も追い出される。そうなれば住むところさえ失う。わかりやすさを優先し、いつか別の時代の言葉で表すなら、路上生活者【ルビ:ホームレス】だ。
だが、ジョンは端くれと言えども貴族だった。耳クソほどのささやかなプライドが残っている。卒業後の進路にぜんぜん当てがないわけでもない。騎士養成学校は、仮にも貴族の子息が通う王立の高等学校だ。その卒業生ともなれば、どんなに不景気であってもほんの少し希望のランクを下げさえすれば、ふたつも選択肢があった。
ひとつは、辺境の国境警備兵。いつ血迷って攻めて来るともしれない東の蛮族をひたすら待って、何もない砂漠を日がな一日監視しつづける。一年勤めると風と話ができるようになり、二年で人間の言葉を忘れ、三年たつと自分の名前が思い出せなくなると言われる、孤独が似合う実に男らしい仕事だ。
もうひとつは、国営の傭兵。形だけウルカン王国騎士団の名を冠し、戦時下の同盟国に大サービス価格で貸しだされ、たいていは最も兵士の消費が激しい最前線を転戦させられる。小金を貯めて三十歳くらいで故郷に錦を飾る者もたまにはいるが、平均寿命は多めに見積もって二十二歳だそうだ。勇気と運を試すにはもってこいの、こちらも国境警備兵に負けず劣らず、涙が出そうなくらい男らしい仕事だ。
どちらの職に就いたにせよ、二度と王都の土は踏めそうもない。ため息がもれそうになったとき、その声は聞こえた。
「ジョン・アスタロット!!」
珍しい名前ではないが、記憶によれば同姓同名のヤツは同級生にはいない。どうやら自分の運は別の、おそらくはどうでもいい場面で使われるらしい。必死に祈ったが望みは天に届かず、ジョンは名前を呼ばれた。
考えてみれば奇跡など起きようもない。全教科、中の上か上の下の成績。おまけに、自慢にもならない五年間の皆勤賞を学年でひとりだけ先週もらったばかり。落第する要因すらない平凡な成績だ……。
「はい!!」
ジョンは、元気に聞こえることを期待しつつ、やけくそ気味に大声で応えた。
壇上にのぼる階段を目指して、中央の通路を練習どおりに胸を張って悠々と歩く。
通路の左側に騎士養成学校の生徒、右側に魔道士養成学校の生徒が整然と並んでいる。
練習と違ったのは、赤い三角帽子をかぶった魔道士養成学校の女生徒たちがいること。青いケープを羽織り、丈の短い真っ赤なローブから白いふくらはぎを少しだけのぞかせている。そして、その彼女らがこちらをチラチラ見ること……。
男ばかりの騎士養成学校では、きちんと継ぎが当たっていてボタンの数がそろってさえいれば、どんなボロを着ていようと誰も気に留めない。むしろ年季の入った服をわざと着て、そのボロさ加減を競う蛮カラな風潮すらあった。式服のボロさも練習中は、さして気にならなかった。
だが、それを同世代の女の子の目にさらすとなれば、ぜんぜん話が違った。この気まずさは、まったく想定外だ。サイズの合ってない式服が急に恥ずかしくなる。
そんなことを今さら後悔しはじめたとき、前方の右で、巻き毛の長い金髪【ルビ:ブロンド】が揺れて、こちらを振り向くのが見えた。
ジョンは、その娘【ルビ:こ】をよく知っていた。
といっても名前すら知らない。隣の魔道士養成学校に在籍する同学年の女生徒。知っているのはそれだけだ。
その娘を最初に見かけたのは入学してまだ日の浅い秋の午後だった。枯れ葉はまだ積もっていなかったし、もしかしたら紅葉すらしてなかったように思う。同級生だろう、真新しい制服を着た二、三人の女の子たちと一緒に談笑しながら校庭の端を歩いていた。
彼女は、とにかく目立っていた。
まずその足どり。地面から三センチくらい浮いているように軽やかだった。それに、今日と同じようにどんよりとした曇り空なのに、彼女の周りだけ光が差しているように見えた。その第一印象は、
――天使って本当にいるんだハ!!
世にも馬鹿げたこの一言でわかるとおり、ジョンは一目で恋に落ちた。
誰かに一目惚れした経験があり、すでにいい大人である読者なら説明は不要だろう。たいていの恋は、あとで冷静に考えれば馬鹿げたものであるから、
――天使って本当にいるんだハ!!
思春期真っ盛りのジョンが本気でそう思ったとしても、まぁ、しょうがない。
そのあと、隣の魔道士養成学校のそばを通るたびに、ジョンは彼女の姿を探した。
背格好は中肉中背。子供のように低い鼻以外は整った上品な顔立ちで、金色の長い髪がいつも輝いて見えた。ただし、美人というだけならきれいな娘は他にも少なからずいた。
ジョンが彼女を好きになった理由は、その雰囲気。とくに笑顔だ。
彼女は、青く澄んだまん丸な瞳の目じりを下げていつもフワフワと屈託なく微笑んでいた。それは子供時代に置き忘れてきたようなどこか懐かしい笑顔だった。
挨拶を交わしたことも三度ほどある。驚いたことに声までがフワフワ。
とにかく彼女ときたら、歩き方も髪の毛も首の傾げ方もあくびのしかたや頬や胸の丸みまで、何もかもがいつでもどこでもフワフワ。
遠くから見ているこっちまで、いつの間にかフワフワと天に昇る心地になってしまう……それこそ天使と呼ぶにふさわしい見えない翼があるかのようだった。
とはいえ、それだけだった。それ以上は五年間、何も進展はない。
なにしろ騎士養成学校では男女交際はご法度【ルビ:はっと】で、それは許婚【ルビ:フィアンセ】がいる者にまで厳格に適用されていた。それに女の子にかまけている場合ではないことくらい、さすがにわかっていた。
――想いを伝えるとしたら正式な騎士になってからだ。
騎士になれると信じていた頃は、そう自らを戒めて辛い修行に耐えていた。名前も知らないその娘は、ジョンにとって恋人であり心の支えでもあった。
今、そのフワフワの天使がこっちを見て微笑んでいる。そう気づいたとき、ジョンは顔から火が噴きだし、突然穴に落ちたかのように目の前が真っ暗になった。
せめて帽子の羽飾りだけは、昼飯を抜いてでもちゃんと真っすぐに立った新しいものに買いかえるべきだった。彼女が最後に見る自分の姿がしおれた羽飾りじゃ、あんまりだ。
思いのほか浮き足立っていたのだろう、六段ほどの階段をのぼり、壇上に足をかけようとした瞬間、ものの見事にジョンは転んだ。
それもただ転んだだけではない。どうしてそんなことになったのかは見当もつかないが、気がつくと足が階段から離れ、背中はえびぞり、全身が宙に浮き、今まで見ていた風景がひっくり返っていた。どうやら後ろ向きに頭から床に激突するらしい……。
人間、死ぬ間際になると時間が止まったように感じるというが、あれは本当だった。
同級生たちの驚いた顔も一人ひとりよく見えたし、魔道士養成学校の女の子たちが一斉にあげた甲高い悲鳴も他人事のように冷静に聞きとれた。同級生の表情や悲鳴の数と大きさから察して、かなりヤバイことになりそうなのもわかる。
その喧騒の中にジョンは、フワフワの天使を見つけた。彼女もこちらを見ていた。だが、彼女だけは、あわてていない。いつもどおりフワフワのままだ。
少しくらいあわててくれれば嬉しかったのに……そう思ったとき、短い杖を手にした天使の口元がかすかに動くのが見えた。
「綿毛【ルビ:フラッフ】」
確かにそう聞こえた気がした。おそらくそれは呪文だったのだろう。ジョンの身体が一瞬わずかに浮きあがり、床にフワリと落ちた。どこにもけがはなかった。
彼女がとっさに杖を振り、魔法を使ったことに誰も気づかなかったようだ。ジョンが立ちあがると、あちこちからホッとしたような失笑がもれた。
彼女のほうに目をやると、そこにはいつもと同じフワフワした微笑みがあった。
――ありがとう。それにしても、君は、使う魔法まで“フラッフ【ルビ:フワフワ】”なんだね。
心の中で感謝しながら、ジョンはその安らかな笑顔が明日には自分の前から消えてしまう寂しさを改めて痛感した。
そこから先はとくに何もない。ジョンは卒業証書を受けとると、何事もなかったかのごとく元の場所に戻り、式も滞りなく進行していった。
騎士養成学校の最後の生徒が壇上からおりると、魔道士養成学校の証書授与に移った。
次々に呼ばれていく名前をジョンは耳をすまして聞いていた。せめて自分を助けてくれた彼女の名前を知りたかったからだ。辺境の地かどこか異国の地で野垂れ死ぬにしても、本物の天使の名前を覚えていれば天国に行けそうな気がした。
彼女の名前は、結局、最後のひとりになるまで呼ばれなかった。
最後のひとり。つまりフワフワの天使は、両校の卒業生の中で今年最も成績が優秀な学生だったのだ。その名前は、
「マリー☆#$・※〒@%Σ」
――えッ?
全神経を耳に集めていたにもかかわらず、にわかに沸きあがった拍手と歓声で、出だしの“マリー”しか聞きとれなかった。
マリーは、場違いなほど軽やかな足どりで壇上に駆けのぼると、魔道士養成学校の校長からうやうやしく証書を受けとった。そして校長と来賓に二校の卒業生を代表し深々とお辞儀をし、フワフワと微笑んだ。また拍手が沸きおこる。
ジョンは、その笑顔に見とれながら、ある決心をしていた。
――思い出をひとつだけ作ろう。
思い切って、謝恩会でマリーに話しかけてみよう。
そうだ、さっき助けてもらったお礼を言えばいい。
そして、マリーの笑顔と声をしっかり胸に刻もう。
そのふたつさえあれば、明日から始まる殺伐とした日々もきっと少しは潤う。一年や二年、もしかしたら三年くらいは耐えられるかもしれない……。
そのとき、ジョンのちっぽけな一大決心を吹き飛ばすような勢いで、壇上から高らかに声が響いた。それは卒業式の最後に行われる儀式“聖ウルカへの誓い”だ。
「健やかなるときも病めるときも、我が身、我が心、常に王国とともにあらんことをここに誓う!! 永遠なれ【ルビ 永遠なれ:マイロ】、ウルカ!!」
マリーだった。いつものフワフワした雰囲気からは想像できないほどしなやかで凛とした声だ。その声に呼応し、卒業生二百人の声が講堂の壁や床を震わせて響きわたる。
「健やかなるときも病めるときも、我が身、我が心、常に王国とともにあらんことをここに誓う!! 永遠なれ【ルビ 永遠なれ:マイロ】、ウルカ!!」
騎士養成学校の生徒はそろいの剣を、魔道士養成学校の生徒はさまざまな杖を、顔の前に真っすぐに立てて掲げ、壇上の国旗に忠誠を誓うと卒業式は閉幕した。
―2―
卒業式のあとは三々五々、生徒たちは、寮や下宿先あるいは親が宿泊しているホテルに行き、夕方からの謝恩会に出席する準備に取りかかる。だいたいは着替えのためだ。
といっても、男の大半は卒業式の式服をそのまま着て出席するから、学内やそのへんのパブで友人たちとひたすらだべって時間をつぶす。
時間がかかるのは、もっぱら魔道士養成学校のお嬢さんたちだ。髪をきれいに直し、夜会向けの派手な化粧をほどこし、この日のために仕立てた豪華絢爛なパーティ用のドレスにお色直しする。
もちろん、ひとりでは着れやしない。上京した母親や祖母の総指揮のもと実家から呼び寄せた下女が三人がかりくらいで寄ってたかって即席の淑女に仕上げるそうだ。
王宮のパーティともなれば、日頃食べられないような料理が山ほど並ぶだろうに、コルセットでギュウギュウに締めあげたお腹じゃ、ケーキのひとつも入らない。それでもパーティが終わる頃には空腹でフラフラしながらも、「私はクッキーひとかけらでお腹がいっぱいですわ。オホホ」みたいな顔でにこやかに笑っていなければならない。
というのも、地方貴族の娘にとって、これから始まる謝恩会は、運がよければ金持ち領主の跡継ぎに見初められるかもしれないし、婿養子にピッタリの将来を嘱望される士官候補生と知り合えるかもしれない数少ないチャンス。噂では、今日ハズレくじを引かないために魔道士の眼力を五年間みっちり鍛えあげる娘もいるそうだ。そんな修行に比べれば、目の前のご馳走を一食抜くくらいは我慢のうちに入らないのかもしれない……けど、女の子も大変だ。
だが、まあ、ジョンには関係のない話だ。サイズの合っていないみすぼらしい式服を一目見れば、ジョンが金持ち領主の跡継ぎでも将来を嘱望される士官候補生でもないのは、魔道士の眼力など使わなくても、すぐにわかるというものだ。
(どうせ……)相手にされないのだから、他の女の子のことはどうだっていい。ジョンの頭の中には、マリーにいつ何をきっかけに声をかけるか、それにマリーがどんなステキなドレスを着てくるのか、それしかなかった。
王宮の西の塔に日が差しかかる頃には、王宮前の広場は、車寄せに入る順番を待つ数十台の馬車で渋滞していた。馬車を引いているのは、きれいに飾られた獅子トカゲ【ルビ:レオザード】や鳥トカゲ【ルビ:バドザード】。トカゲタイプの代表的な大型幻獣【幻獣ルビ:ミラージュ】だ。
“幻獣”という名は、その生態があまり知られていなかった昔、突然現れ、突然消えてしまう、別世界の不思議な生き物と信じられていたことに由来する。実は今でもそう信じている人は意外といる。だが、大半の人の認識は、ウルカン王国以外の地域では滅びてしまった、けっこう珍しい生き物、その程度だろう。
幻獣には、神か悪魔かあるいはいかれた魔道士の所業か、いくつかの生き物を強引に混ぜたような特徴を併せもつものが多い。
たとえば、獅子トカゲは、頭はトカゲで胴体は獅子のようながっしりとした身体つきの幻獣だ。全体の大きさは種牛ほど。額の左右と鼻先に合わせて三本の巨大な角をもち、頭から首にかけて紫のたてがみを生やし、膝から下も同色の毛におおわれている。
鳥トカゲのほうは、頭の形と二本脚で立つ全身のシルエットが鳥に似ている。ただし、派手な羽毛が生えているのは、翼に似た前肢と頭頂だけ。それ以外の部分は、トカゲのようなこげ茶の鱗でおおわれていて細長い尻尾もある。大きさはロバと馬の中間くらいだ。
二種ともいかにも獰猛そうな顔つきだが、馬車に使うものは、さすがによく躾けられていて鳴き声もあげずじっとしていた。
馬車に乗っているのは、あでやかなドレスに身を包んだ魔道士養成学校の女生徒たちだ。赤、ピンク、黄色、紫……まるでさまざまな種類のバラが同時に咲き乱れる庭園のように色とりどりだ。
その華やかな光景を横目で眺めながら、ジョンは貧乏仲間の友人たちと馬車の横を自分の足でトボトボと歩いていた。
「あの娘【ルビ:こ】が一番きれいだよな」「いやいや、こっちの娘のほうがかわいい」と友人たちは無責任な品評を熱心に続けている。ジョンはそれに適当に相づちを打ちながらも、目はマリーの姿を懸命に探していた。だが、結局、見つけられなかった。
謝恩会の会場である王宮の大広間は、城の中ではなく隣に併設された別棟だ。大きなパーティや会合のために比較的新しく、といってもジョンが生まれる以前だが、建てられたものらしい。
入口の左右には、長槍を誇らしげに立てた若い衛兵が十人ほど整列し、女性だけを愛想よく出迎えていた。その出で立ちは、騎士養成学校の式服の元になっただけあって、ジョンたちの服装とよく似ている。違っているのは、帽子の赤い羽根がウサギの耳のような形で二枚ついていること、それに背中の真ん中で赤と青に縦に分割されたマントを羽織っていることくらいだ。
その派手でマヌケな衣装こそが、五年間、いや小学舎に通っていた五年間を合わせれば十年……、ジョンがあこがれ続けた王宮詰めの騎士が着用する制服だった。だが、それも採用枠がすべて埋まった今となっては関係ない。
会場の大広間は、すべてが圧倒的だった。五学年全員が整列できる学校の中庭より何倍も広く、天井は三階建ての校舎より高い。
奥の壁には卒業式と同じく巨大な国旗が飾られ、一段高くなったところに金の玉座が置かれている。玉座の右手には四十人ほどの管弦楽団が控え、左手には大勢の給士と大量の料理が出番を待っている。
大広間の床は、両校の卒業生とその縁者の人いきれであふれていた。鏡張りの天井には、何百本ものロウソクを立てたシャンデリアがいくつもぶらさがっている。その光が、手の込んだ彫刻と極彩色の絵画で埋め尽くされた壁を余すところなく照らしだしている。
もうじきパーティが始まろうというのに会場のどこにもマリーの姿はなかった。ジョンは、マリーの到着を心待ちにしながら、壁の絵を所在なげに眺めている。
ジョンがぼんやりと観ていた絵は、国王の先祖、追っ払い【ルビ:オッパライ】王“聖ウルカ”が建国の際に打ち立てた数々の伝説、それに奇跡を描いたものだ。
ジョンがマリーの到着を待っている間に、読者には、聖ウルカの偉業と王国の成り立ちや特徴を簡単に紹介しておこう。
ウルカン王国の起源は、おおよそ二百五十年前にさかのぼる。当時この地域は、魔族により荒廃し“呪われた地”と呼ばれていた。魔族は、本来おとなしい幻獣を猛り狂う怪物に変え、たびたび人間の町村を襲った。
その悲惨な状況から人々を救った英雄こそが現国王の先祖、国名にその名を残す“聖ウルカ”だ。彼は、相棒の真っ白な獅子トカゲ“ビビババ”にまたがり国中を駆けまわり、幻獣たちを魔族の手から解放。ついには魔族をこの地から追い払い、その首領である魔王を地の底に封じたと伝えられる。この伝説から、聖ウルカは“追っ払い王”のふたつ名で呼ばれている。
もちろん、魔族などというものは誰も見たことがないのだから、この伝説のどこまでが事実なのかはわからない。だが、建国以来二百五十年、ウルカン王国を如才なく治めてきたのは、聖ウルカの子孫である代々の国王たちであり、特殊な慣習や珍しい地名や家名、ピルビス市の幻獣レースを始めとしたユニークな祭りなど、この国には伝説に由来する独自の特徴が数多く現存するのも確かだ。
中でも一番の特徴は、他国ではほとんど見られなくなった幻獣たちが、牛馬や犬猫と同様、人の身近にいることだろう。ただし、長引く不況のあおりでエサ代がかさむ大型幻獣の数は、ここ十年で激減したと言われている。それでも幻獣はステータスシンボルであるという古い価値観は依然として残っていて、富裕層を中心に数百種、数万頭の幻獣が今も国中で飼われている。
主催者である王様も着席し、すでにパーティが始まって二時間あまりが過ぎていた。
未だマリーは現れない。ジョンはマリーの姿を求めて、歓談する生徒や教師の間を歩きまわり会場を何周もしていた。おかげでヤケ食い気味につまんだ料理で腹はパンパン、誰かれなく勧められるままに飲んだ酒で足元が少しおぼつかなくなっている。
見れば、料理が載ったテーブルが少しずつ片づけられていた。そろそろ王様が楽団に合図を送り、舞踏会が始まる。それが終われば今夜の謝恩会もお開きとなる。
つくづく俺には運がない。せっかく一念発起したというのに当のマリーが来ないではどうしようもない。お笑いだ。五年間の締めくくりがこれかよ……。
「あ~ぁ、どうせ」
ジョンの口から我知らずため息がもれたとき、王様がおもむろに立ちあがった。楽団のほうに目をやっている。皆、その雰囲気を悟ったようだ。会場のあちこちで即席カップルがどんどん出来あがっていく。
実を言えば、ジョンはこの舞踏会をちょっと楽しみにしていた。ダンスの経験がある同級生を探しだし、ルームメートのマイケルと夜な夜な寮の廊下で汗だくになってレッスンを受けたほどだ。
だがそれも無駄。今からじゃ、ダンスのパートナーは見つかるわけがないし、だいたいサイズの合ってない式服を着た男と踊ろうという物好きな女の子なんていやしない、とあきらめかけたところに、
「あのォ……」とかたわらから遠慮がちに声がかかった。
黒いドレスを着た小柄な女の子だった。おそらく魔道士養成学校の生徒だ。なんとなく見覚えがあるようなないような……。さっきちょっと妙な味の酒をくれた娘だったかもしれない……と、そこまで考えをめぐらせたあとで、鈍感なジョンはやっと気づく。
――もしかして、この娘、俺にダンスに誘ってほしいのかも?
しかし、見れば見るほど変わった娘だった。黒いドレスは宝石がちりばめられたかなりの高級品で仕立てもよさそうだ。なのに、採寸を間違えたのだろうか、肩からずり落ちそうだし袖も折り返している。髪型は赤い髪を後ろでひとつに結んだだけ、装飾品の類は一切なし。口紅だけが異様に赤い。それに目まいがするほど濃厚な香水をつけている。
そりゃまあ、わざわざ俺に声をかけてくるくらいだ。変わった娘にはちがいないか。
(どうせ……)マリーはもう来そうもないし、元もと俺にダンスの相手を選ぶ権利などありはしない。声をかけてくれただけでもありがたいというものだ。
それによく見れば、いかにも気が強そうなナイフのような目を伏せてモジモジしている様がけっこうかわいい。いや……メ、メチャかわいい……気がしてきたぞ。おそらくここにいる誰よりもかわいい!! もしかして国中で一番かも!? 案外、この娘が俺の運命の女性かもしれない。そうだ、間違いない。いっそ今すぐプロポーズしたいくらいだ。
酒に酔ったせいだろうか、そんな突飛なことまで頭に浮かんでいた。
その変わった女の子は、頬を赤らめながら恥ずかしそうにこちらに手を差しだす。手袋ははめていない。子供みたいな小さくてかわいらしい手だ。
ジョンは、その小さな手をとろうと、できるかぎりの優しい笑顔を向けた。だが、その笑顔は、突如嵐のように大広間に駆けこんできたけたたましい声に一瞬で消し飛ぶ。
「ちょっと待って!! ちょっと待って!! ちょっと待ってくださいませ!!」
その異様によく通る声の主に会場にいた全員の耳目が集まる。ジョンも思わず大広間の入口を振り向いた。
「舞踏会、まだ始まってませんわよね? 私、間に合ったでしょうか?」
長い金色の巻き毛はほつれ、額には大粒の汗が浮かび、肩で大きく息をしていた。
それでもいつもと変わらずフワフワと微笑んでいたのは、
――マリー? ? ? マリーだ!!
マリーはドレスの裾を持ちあげて、広間の奥に向かって真っすぐに駆けてゆく。
その意図を察した人たちが、呆気にとられながらも波が引くように道を開ける。
マリーが突き進む先に待ちかまえていたのは……、なんと王様だった。見れば、王様は、周囲の家臣たちを手で制している。
「安心するがよい。あわてずとも舞踏会はまだ始まっておらぬよ。だが、それにしても、ひどい遅刻。それにそのドレス、少々場違いなようだが、いかがした?」
「ごめんなさい。用意しておりました私の黒いドレス、どなたかが間違えてお召しになっていかれたのか、消えちゃったみたいで。それで大あわてで街中の店を探したのでございますけど、あいにくこれしか残ってなくて。でも、ほら……」
マリーは、王様の前だというのに臆する様子が見受けられなかった。まるで以前からの知り合いのようだ。いつもと同じようにフワフワと優雅に微笑んでいる。でも、ほんの少しだけ頬が引きつっているようにも見える。
「いずれ使うものでございますから……、でも、やっぱりちょっと派手でしたかしら? テヘ」
「いや、とても似合っておるよ。ただ、そのドレスに見合う男がここにいるかどうか、そこが問題かもしれぬがな」
「えーっと、たぶん大丈夫ですわ。当てがございますから」
「そ、そうか。それは何よりだな。では、その男のもとにすぐに行くがよい。じきに舞踏会を始めるからね。あぁ、あとでその幸運な男を連れてきなさい。どんな顔をしているか、ぜひ見てみたい」
王様が必死に笑いをこらえているのがありありとわかった。
マリーは王様に一礼すると振り返り、キョロキョロとあたりを見回している。
王様が笑いをこらえていたのには理由【ルビ:わけ】がある。
マリーのドレスだ。王様が仰ったとおり、とても似合っているとは思う。
だけど、どう見てもマリーが着ているのは、純白のウエディングドレスだった……。